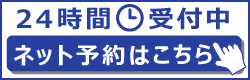皆様、すっかり寒くなりましたね。インフルエンザがいつもより早く流行しているようなのでお気をつけ下さい。
さて、このたび歯周内科の講習を再受講し内容も更新されました。そこで最新の知識も加えて再度歯周内科について解説していきたいと思います。
歯周病は成人の約8割が罹患する虫歯と並ぶ歯の感染症の病気の2大疾患のひとつです。歯周病は軽症のうちは自覚症状がほとんどなく、歯ぐきが赤くなり時々少し歯茎から出血するくらいの問題しか起こりません。しかし、病状が進行すると治りにくくなり(歯周組織が壊されると元に戻らないことが大部分です)治療も大変になってきますので早期の対応が重要です。
それでは通常の歯周病の治療を説明してみましょう。
まずレントゲン写真と口腔内写真、歯周組織検査、口腔内の汚れの確認を行います。
歯周組織検査では歯と歯茎の間に歯周ポケットという歯茎のポケット状の隙間があり、この深さを専用の金属製のプローブで計測します。歯肉の出血状況、排膿の有無、歯の動揺の有無も記録します。歯周ポケットが4mm以上、出血あり、動揺度1以上を以上として診断します。
レントゲン写真では骨吸収の進行や歯根膜の状態を確認し、歯周組織の検査結果と併せて歯周病の重症度やかみ合わせによる外傷の問題など他の要因も考えに入れて歯周病を診断します。
歯周病の分類
歯周病の分類は国際的には悪性度に対する評価グレードA~Cの3段階、進行度に対する評価ステージ1~4の4段階に分けて評価します。
当院では患者さんに対しては以下のように分類して説明しています
1.歯肉炎
病状の進行状況:歯周病の初期段階
歯周ポケットの深さ:4mm以下
症状:歯肉の表面の発赤・腫脹、歯肉からの出血、口臭など
歯周組織の破壊:見られません
治療:歯面清掃、浅い部分の歯石の除去
予後:良好、元通りになる
2.軽度歯周病
病状の進行状況:歯周組織が破壊され始めた状態
歯周ポケットの深さ:4~5mm
症状:歯肉炎の症状に加え、歯の動揺、歯茎の違和感、やや強い口臭など
歯周組織の破壊:骨吸収が始まっています
治療:歯面清掃、歯周ポケット内の歯石の除去、咬合調整
予後:治りやすいが、完全に元通りにならないことがある
3.中程度歯周病
病状の進行状況:歯周病がはっきり進んできた状態
歯周ポケットの深さ:6~7mm
症状:歯茎がいつも腫れて出血します。歯がぐらぐらしてきて噛むと違和感が生じます。ひどい場合は膿も出て口の中がねばねばしたり、口臭がひどくなります。歯茎も痛い、ひどく歯がしみる
歯周組織の破壊:骨が半分近く壊され吸収してきています
治療:軽度歯周病に加え、歯周ポケット深くまで汚染された歯根面の掻把や歯周外科が必要です
予後:治すのにかなり時間と労力が必要です。これ以上進行させないことが目標となります
4.重度歯周病
病状の進行状況:歯周病がかなり進行して危険な状況
歯周ポケットの深さ:8mm以上
症状:歯の激しい動揺(咬むと沈み込む)、歯根露出(歯が長くなった)、歯茎の激しい腫脹、全顎的な歯肉よりの排膿、痛くて咬めない、歯の挺出、激しい口臭など
治療:残せるかどうかの診断になります。治る見込みもなく残すことがリスクとなれば抜くことが推奨されます。動揺して痛くて噛めないところは暫間固定という歯と歯を接着剤や仮歯でつないで動きずらく固定したり、歯を削って強く当たらなくします。
他中等度歯周病と共通ですが、抜歯対応が多くなります
予後:経過が悪く残す選択をしても、病状の進行が止まらなければ抜歯となることが多いです
以上が歯周病の分類と特徴です。
治療にもどりますが、保険での歯周病治療には決められた流れがあって、それに沿って進めていかなければなりません。
先ほどの治療の流れでは歯周組織検査まで行ってます。
次にスケーリングという主に歯肉より上についた歯石という歯の表面にこびりついた細菌の塊を全部の歯から取り除いていきます。通常1~2回にわけて行いますが、何年も放置していて除去が困難な場合は最大6回に分けて行います。
これが終わって、1週間以上経過したら、再度歯周組織検査を行い、歯肉の状態を再評価します。
今度は歯周ポケットが4mm以上計測された歯を中心に歯肉縁下歯石の除去を行います(SRPと言います)。ここが一番重要で、縁下歯石は歯周病の原因菌が潜んでいる中心で、嫌気性菌である歯周病菌が好んで存在しています。これを専用の器具で取り除いていくのですが、痛みを伴いますので歯肉に麻酔をかけてから行うことが多いです。
これは当医院では歯科衛生士が専門に行っています。見えないところを手探りで丁寧に取り除いていきますが、術者の負担や患者の苦痛を伴います。歯周病が軽度であれば楽で、病状が進んで重症になればなるほど大変で、治療の成功率が下がります。これを1/4~1/6のブロックに分けて行いますので、通常全部で4~6回にわけて行います。
こうして全てのSRPが終わって2週間以上経過したら、3回目の歯周組織治療を行い、改善状況を調べます。
改善がみられるところは歯周ポケットの深さが浅くなり、出血や動揺が改善されます。
その一方で反応が悪く改善がしないところは再度SRPをするか、次の段階の歯周外科に移行するか、悪化させないことを目標のメンテナンスへ移行するかになります。
再度のSRPや歯周外科は歯石の取り残しがあることを想定して行います。
歯周外科とは歯肉を切開して歯根面と歯石が見えるようにして、明示下で直接歯石や不良肉芽組織を取り除き、歯周ポケットの正常化を狙います。
そのほか、歯の清掃状況のチェックと清掃指導で口の中の環境を良くしていき、細菌が定着しずらい環境に変えていくことが重要です。
さらに歯によろしくない方向の力が常にかかったり、過度の力がかかることでも歯周組織は破壊され、それが急速に進行するので力のコントロールも非常に重要です。そのために歯を削ってかみ合わせの調整を随時行っていきます。
こうして全ての歯周病の治療が段階的に行われ、最後の歯周組織検査を行い、まれに再度のSRPや歯周外科を行うこともありますが、通常は歯周病安定期治療(SPT)あるいは歯周病重症化予防治療の定期メンテナンスのフェーズへ移行します。
昔はこのような予防管理の保険項目はなく、定期的にメンテナンスするのは大変でした。
ただ、せっかく苦労して歯周病の治療をしても、そのあとのメンテナンスへ来なかったり、清掃が不十分だったりすると歯周病は容赦なく再発してきます。歯周病の治療は全体的に重症で、被せ物までいれると容易に1年以上かかります。
そのため通常は3か月に一度、被せ物が多かったり、深い歯周ポケットが残ったままだったり、排膿が残っていたり、口腔の清掃が出来ず、常に歯茎は赤くはれている人はもっと短い間隔でメンテナンスしています。
それでも時々歯周病が急発して歯を失ってしまうこともあります。
歯周病との戦いは水回りの掃除と似ています。
お風呂場を例に挙げると、定期的にお掃除しないと床には水垢の赤いカビが発生し、壁のタイルのつなぎ目には黒いカビが発生します。これを洗剤と専用ブラシを用いて機械的に取り除いて床面や壁面をピカピカにしていきます。
せっかくきれいにしても定期的な清掃をさぼればさぼるだけカビが広がり、しつこくこびりつきます。
汚れが付くのは細菌が原因なのですが、注目したいのはきれいになってもまた汚れてくる(再発する)、汚れの除去は落としやすいように薬品や洗剤を使いますが、基本的には機械的に落とします。これは歯の表面に付着したバイオフィルム(プラーク)や歯根面に付着した歯石除去も同様で、結局歯周病の治療の中心は保険では機械的主義が中心となっています。
あれ、歯周病は細菌の感染症なのに、菌が住みつきづらくすることが中心で、菌に対する直接の検査や治療はどうなっているのと思いませんか?
そこで歯周内科の登場です。続きは次回にしましょう。